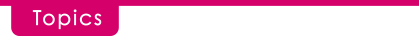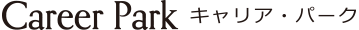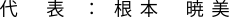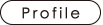研修のテーマは『学生対応力』。受講して頂いた大学職員の皆様は、関東から中部、関西、中国、九州の大学で主に教務課、学生課に所属されていらっしゃいます。内容としては、大きく2点です。大学を取り巻く社会の現状と学生の多様化の理解、そして対応力を高めるためのコミュニケーション能力向上です。それらについて大学、学生、自身の3つの側面から現状と課題についてグループや個人ワークを通して考えて頂きました。
私が研修を行ううえで大事にしていることは、参加して頂いたご自身が気づきを得てご自分と向き合って頂くことです。せっかく日常業務から離れ様々なことを客観化できる時間です。一方通行的に講義を聞いて帰る、ではもったいない!聞いて、考えて、気づいてのサイクルが回って初めて課題と捉えていることが自分事となり思考や行動につながっていくと思います。今回もグループでの対話やワークを盛り込みましたがあっという間に終了時間になり、受講された方々からも「一日の研修は長いのだろうな~と朝は思いましたが、あっという間でした!」とのお声を頂きました。研修開始時は、初対面同士、少し緊張されていらっしゃいましたが午後のコミュニケーション・エクササイズでは以前からのお仲間では?と思うくらい打ち解けとても良い雰囲気で研修終了を迎えることが出来ました。
社会の変化のスピードに大学は以前より増して敏感になっていると感じます。18歳人口が平成4年にピークを迎える一方で新設の大学や学部が反比例するように増加の一途をたどり収容率も向上しました。そして私立大学の定員割れは継続されています。大学という『場』がユニバーサル化されている中で社会からのニーズに対応する取り組みを策定し地域との関係性の向上と大学が取り組む課題は様々です。また学生の学力向上、就職状況やマナーなど社会から向けられる目が厳しいものとなっています。
この『学生対応力』研修は、私大職員研修センター様では定番研修として位置付けて頂いており毎年、開催をさせて頂いているのですが年々、受講して頂く方の意識の変化を感じます。今回もグループディスカッションを通して数年前では出てこなかった発言等が各グループ共通して現れ教務課や学生課で勤務されている方々のステークホルダーの多様化と悩みを強く感じました。そしてだからこそ研修にも真摯に取り組んで頂き私自身は、ありがたくもあり身が引き締まる感覚を覚えました。真摯に向き合うと葛藤を味わうことがあります。また支援をすることは自分と向き合わざるを得ないことにもなります。しかしそれは、真摯に取り組んでいるからこそ。葛藤を恐れずにやって行きたいと思います。
こからもこれまで以上に受講して頂く職員の皆様に様々な『気づき』の場の提供者として私自身も研鑽して行きます!